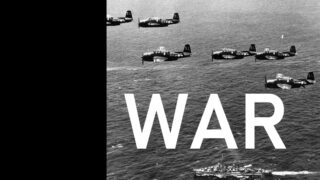 昭和二十年以前
昭和二十年以前 戦ふ兵隊(昭和14年)
日本陸軍の雄姿を映像に収めたドキュメンタリー映画は亀井文夫監督の手に委ねられたのですが、完成した作品は雄姿どころか繰り返される転戦で疲弊していく兵隊の姿がリアルに記録されていて、せっかく作った映画は結果的にはお蔵入りとなってしまいました。
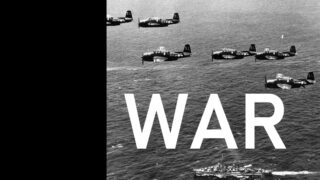 昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前 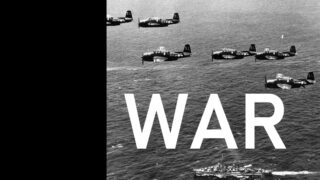 昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前  昭和二十年以前
昭和二十年以前