 外国映画
外国映画 ウエストワールド(1973年)
マイケル・クライトンは小説家でもあり映画監督でもあり脚本家でもあるオールラウンダー。1990年に書いた小説「ジュラシック・パーク」はスティーヴン・スピルバーグとユニバーサル・ピクチャーズに50万ドルで映画化権を売ることになるのですが、本作は公開当時、やや毛色の変わったB級大作といった感じでした。今見ると確かに『ジュラシック・パーク』につながる内容になっているところが興味深いです。
 外国映画
外国映画  日本映画
日本映画 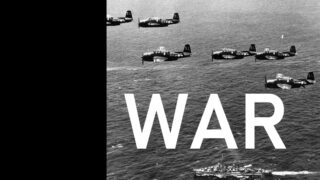 外国映画
外国映画 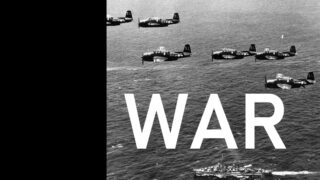 外国映画
外国映画  昭和二十年以前
昭和二十年以前  1940年代
1940年代  日本映画
日本映画 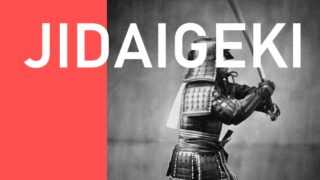 日本映画
日本映画  外国映画
外国映画  日本映画
日本映画