 昭和二十年以前
昭和二十年以前 生きてゐる孫六(昭和18年)
昭和18年7月公開の松竹映画『花咲く港』でデビューを果たした木下恵介の監督第二作で、同年11月に公開されました。脚本も木下恵介のオリジナルで、名刀「関の孫六」をモチーフにしながら因習に縛られる地方の村での騒動を喜劇的に描いています。
 昭和二十年以前
昭和二十年以前  日本映画
日本映画  昭和二十年以前
昭和二十年以前  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画 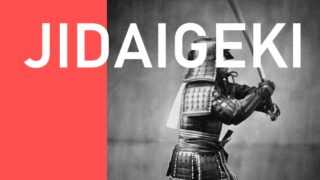 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画 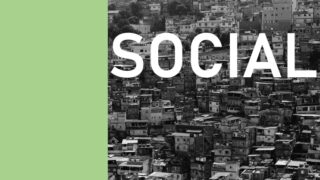 日本映画
日本映画