 昭和二十年以前
昭和二十年以前 恋も忘れて(昭和12年)
清水宏監督は前年に『有りがたうさん』、本作を公開したあとに年末には『風の中の子供』を製作していて、自然の中でのロケーション撮影を行った二作と比べると、この『恋も忘れて』は松竹蒲田時代のサイレント作品『港の日本娘』に近いテイストに仕上がっています。
 昭和二十年以前
昭和二十年以前 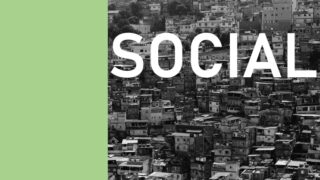 日本映画
日本映画 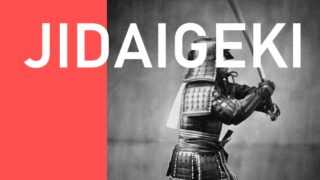 日本映画
日本映画  昭和二十年以前
昭和二十年以前  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画