 日本映画
日本映画 戦国無頼(昭和27年)
原作はサンデー毎日の連載された井上靖の小説で、脚色したのは稲垣浩と黒澤明。信長による城攻めで主君を失った落ち武者三人を主人公にして、そこに盗賊の娘と官女がからんで波瀾万丈の物語が繰り広げられます。
 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画 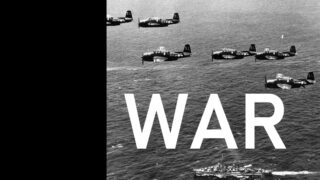 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画 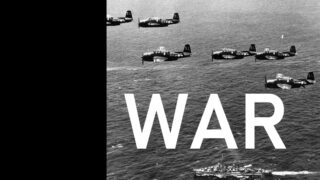 昭和二十年代
昭和二十年代  日本映画
日本映画 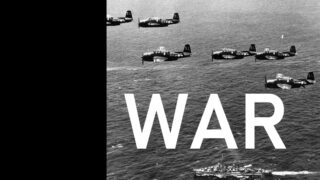 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画