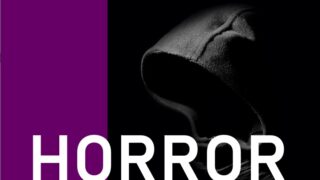 1940年代
1940年代 キャット・ピープル(1942年)
セルビアに伝わる猫族伝説をテーマにしたホラー映画で、RKOスタジオが15万ドルという低予算で製作したのですが興行的には400万ドルを超える大ヒットを記録しました。続編というか後日譚の『キャット・ピープルの呪い』が二年後に作られました。
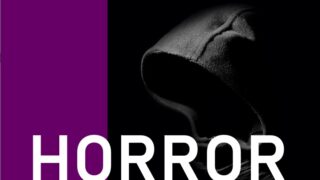 1940年代
1940年代  1940年代
1940年代  外国映画
外国映画  外国映画
外国映画  1950年代
1950年代  日本映画
日本映画 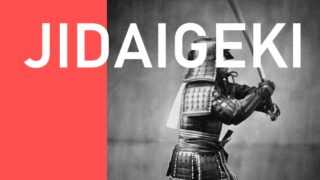 日本映画
日本映画  外国映画
外国映画  日本映画
日本映画  1940年代
1940年代