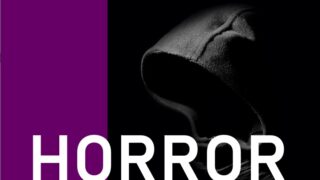 日本映画
日本映画 盲獣(昭和44年)
昭和6年(1931年)に江戸川乱歩が発表した小説「盲獣」を白坂依志夫が大胆に脚色、増村保造が監督しました。TVに観客を奪われた日本映画界が凋落する中で大映は昭和46年末についに倒産してしまうのですが、本作は大映末期に製作された作品でもあります。
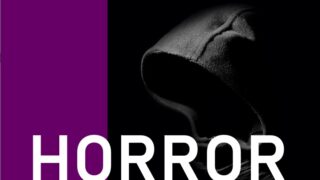 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画 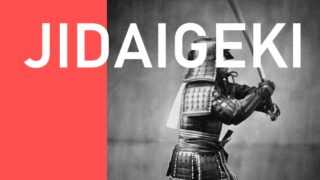 日本映画
日本映画 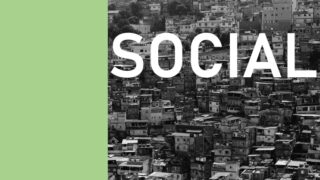 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画 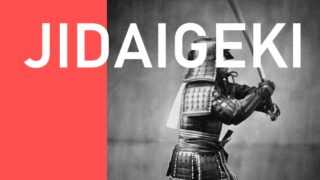 日本映画
日本映画 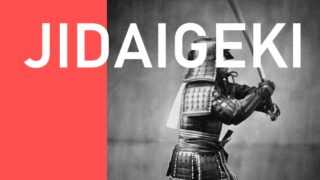 日本映画
日本映画 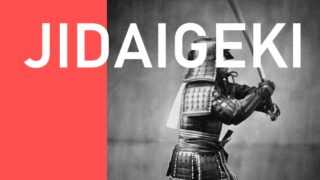 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画