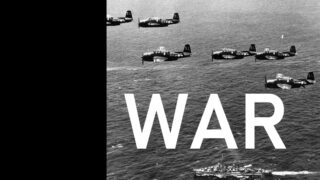 外国映画
外国映画 砂漠の鬼将軍(1951年)
エルヴィン・ロンメルはアフリカ戦線で英国軍と戦った英雄で、大戦中のドイツではヒトラーに次いで国民から人気があったとか。そのロンメルがどんな人で、ドイツ軍の中でどのように振る舞い扱われたのかを丁寧に描いていますので、ヨーロッパ戦争の勉強にもなる映画です。
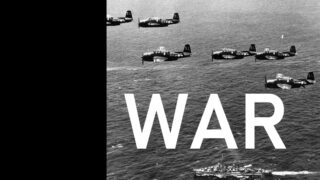 外国映画
外国映画  日本映画
日本映画  1940年以前
1940年以前  日本映画
日本映画  1950年代
1950年代 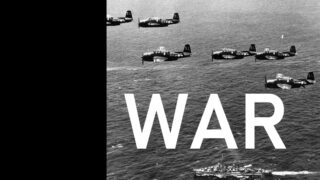 昭和二十年以前
昭和二十年以前  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  昭和二十年以前
昭和二十年以前 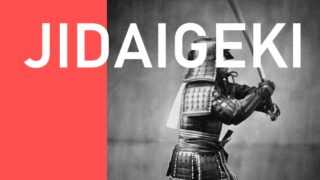 日本映画
日本映画