原節子主演で製作された日独合作映画の伊丹万作監督による日英バージョン
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、伊丹万作監督の『新しき土』です。戦前に日本とドイツが共同製作した原節子主演作にはふたつのバージョンがあり、DVDなどで見られるのはアーノルド・フィンク監督の日本語&ドイツ語版ですが、同時に伊丹万作が監督したものもあり、本作はドイツ語部分が英語に差し替えられています。昭和12年2月に帝国劇場で1週間公開されたのが本作で、その後フィンク監督版が2週間上映され、大ヒットを記録することになりました。
【ご覧になる前に】フィンク監督が抜擢した原節子は撮影当時十六歳でした
海辺の漁民たちが見あげる富士山は冠雪していて山頂に近づくとそこには噴煙が上がっています。雛人形が飾られた農家の老夫婦に電報が届くと、それは息子の輝雄が帰って来るという知らせでした。地震の揺れに襲われた翌日、絹工場で働く妹も「お兄ちゃんが帰って来る」と喜び、大きな鳥居がある邸宅に住む日本髪の娘も感激して鹿に餌を与えてます。ドイツ留学を終えた輝雄は大型客船のデッキで金髪女性のゲルダと語らい、動力機関を見下ろして日本人が作ったと話すのですが…。
明治に生まれた川喜多長政はドイツ留学中に見たオペラ「蝶々夫人」での日本人の描かれ方に反感を覚え、日本の真の姿をヨーロッパに伝える必要があると決意します。帰国後に東和商事を設立した川喜多長政はまず日本に外国映画を紹介することから始めようと妻かしことともに世界中の映画を買い付け、日本最大の映画輸入業者として知られるようになっていきました。
川喜多長政が満を持して映画製作に取り組んだのが日独合作による東洋と西洋の交流の物語で、東宝になる前のJOスタヂオと製作体制を整えます。当時は昭和7年に満州国が成立したばかりで、昭和8年に日本は国際連盟を脱退、時局は戦争へと突き進んでいた頃。昭和11年には日本とドイツの間で日独防共協定が締結され、川喜多長政の映画は両国政府の目に留まるところとなり、製作費の支援を受けるとともに内容も日独の親善や相互理解を深めるものへと変わっていったのです。
脚本を書いたアーノルド・フィンクは地質学の博士号を持ち、山岳映画を得意としていたドイツの映画監督。ハリウッドに渡ったジョゼフ・フォン・スタンバーグとも交友があり、本作撮影時に軽井沢まで訪ねてくるほどだったとか。フィンクは「火山の国」としての日本を強調して、地震や噴煙などの場面を織り込んだ脚本を仕上げました。日本側から共同監督として選ばれた伊丹万作は『国士無双』や『赤西蠣太』を監督して、勇ましくない武士をコミカルかつシニカルに描いて高い評価を得ていましたが、本分は橋本忍を育てたシナリオ作家にありました。共同監督を要請されても監督は本業ではないと固辞したそうですが、断り切れずにフィンクと伊丹万作の共同監督作品として製作が進められることになりました。
しかし外国人の目で日本の風景や文化を切り取ろうとするフィンクと登場人物をリアルに描きたい伊丹万作では方針が合致するはずもなく、やがて二人の意見が対立して、同時に別々の映画が作られることになってしまいました。「撮影に二倍の時間と労力を費やし一年間を浪費した」と伊丹が振り返った通り、日本語とドイツ語のフィンク版と日本語と英語の伊丹版は言語の違いだけでなく、脚本や展開も微妙に異なる作品として完成されたのでした。
主演の光子に抜擢されたのが当時十六歳だった原節子。本作の準備のため来日して萬平ホテルに滞在していたアーノルド・フィンクは二二六事件に遭遇したということですので、昭和11年2月には製作が始まっていたことになるのですが、日活による『河内山宗俊』の撮影を見学したフィンクが現場で原節子を見初めたんだそうです。『河内山宗俊』の公開は昭和11年4月なのでちょうどフィンクの来日時期と合っているのでこの話は本当のようですね。また、サイレント期にハリウッドを制覇した早川雪洲はヨーロッパを経由して日本に帰国していた時期で、アメリカやフランスでの知名度が抜群だったということから日独合作映画に適役だと判断されたのかもしれません。
昭和12年2月に帝国劇場で伊丹版が公開され、翌週からはフィンク版が上映されると、日独防共協定の効果なのか全国で大ヒットを記録することになりました。ドイツではもちろんフィンク版のみが公開されることになるのですが、ナチスが遠い同盟国日本を理解するために本作が有益であると訴えてプロパガンダに利用しようとしたことからゲッベルスによる宣伝工作の対象となり、日本から川喜多夫妻と原節子が招かれてドイツ各地の映画館で挨拶に駆り出されることになりました。当時はシベリア鉄道を使って2週間かけてドイツに渡ったそうで、原節子の後見人として随行したのが熊谷久虎。原節子の義理の兄にあたる熊谷はこの後も原節子に多大な影響を与え続けることになるのでした。
【ご覧になった後で】ただただ原節子の美しさに見惚れるための映画でした
いかがでしたか?鯉に餌をやる初登場シーンから原節子の空前絶後の美しさに目が惹きつけられるばかりで、映画の内容よりも原節子の映像を見られるという愉悦に浸るばかりの作品でしたね。日本髪も着物姿も洋装も足袋だけで火山を登る姿もどれもこれも美しいというほかに表現のしようがないくらい、原節子こそが日本映画が生んだ最大にして最高のミューズであったことを証明する映像でした。もちろんその美しさは高潔な品格に支えられているわけで、原節子本人に会うことはできなくても、実際の原節子自身が教養もあり茶道や華道などを究め完璧な敬語を操りTPOを弁えそれでいて常に素直に内面を表出できる女性であったことは間違いありませんって褒め過ぎですけど。それくらい原節子を見惚れるためだけに存在するような映画だったと思います。
伊丹版は冒頭に「地理的に変なところもあるけど見逃がしてね」的な字幕が出る通り、京都の屋敷の裏には宮島の大鳥居があり、鯉がいる池の横にはなぜか鹿がたくさんいて、その屋敷からバスに乗るとほどなく焼岳があって着物姿のままで火口近くまで行かれてしまうという矛盾だらけの設定になっていました。ここらへんはアーノルド・フィンクが全国を観光気分で撮影しまくったフィルムが使われているため差し替え不能だったんでしょう。字幕でエクスキューズを入れたのは伊丹万作の精一杯の反抗精神の表れだったのかもしれません。
アーノルド・フィンク原作とクレジットされている通り、基本的なストーリーはアーノルド・フィンクが作ったものだと思われます。日独合作と聞くと日本とドイツを舞台にした二国間を行き来する物語が想像されますけど、全くそんなことはなく純粋な日本映画に英語を話すドイツ人ゲルダが登場するというだけのお話なので、めちゃくちゃスケール感の小さいローカル映画だったのには驚かされました。しかも映画の本筋はドイツ留学でヨーロッパにかぶれた男が日本の家族制度に疑問を感じ養子先の娘との結婚に異を唱えたもののやっぱり日本人同士で結婚して満州の新しき大地を耕すという単純なものになっています。ゲルダさんも途中で物語から姿を消してしまうので、わざわざ日独合作にした意味はなかったような気もしてきました。
しかしながら原節子の存在以外に多少の見どころはあるわけで、焼岳に向って歩いていく原節子の後ろ姿を撮ったショットの中でふたつくらいベストショットがあって、構図や雲の流れ方、山肌の捉え方が素晴らしい映像でした。キャメラマンはリヒャルト・アングストというドイツ人で、本作がきっかけになったのか昭和13年に松竹が製作した『国民の誓』というこれまた日独合作映画で再び撮影を担当することになりました。
演出的に見応えがあったのは原節子との婚姻を断った小杉勇が夜の街を飲み歩くシークエンス。ジャズ演奏家のクローズアップが重ねられ「ダイナ」の音楽が鳴り響くところに、いきなり三味線をもった流しの女が現れ、ジャズと三味線の音楽が重ね合わさるところは、たぶん西洋的な思考と東洋での出自の相克を表現していたのでしょう。その両方を否定も肯定もできない小杉勇の悩みみたいなものが、セリフひとつないのに観客に伝わってくる感じがして、ここはもしかしたら伊丹万作のオリジナル部分なのかなと思ってしまいました(フィンク版を見ていないので断言はできませんけど)。
日本映画史的にはドイツに渡った原節子がゲッペルスと並んで映った写真が残されたこともあって本作は国策映画だと勘違いされているようです。けれどもそんなことはなく、元々の始まりは川喜多長政が日本の本当の姿を西洋に伝えるためのものだったわけですし、内容的には戦意高揚的な側面はほとんどなく、ジャンル的にはロマンスものに入る作品でした。オペラの「蝶々夫人」のデタラメさに違和感をもった川喜多長政は、昭和30年に八千草薫主演の『蝶々夫人』を総指揮することで念願を果たしたようですので、この『新しき土』はそのための貴重なステップになったことは間違いないでしょう。いずれにしても原節子の存在を世界に広めたのならば、それだけで本作は十分にその役割を果たしたのではないでしょうか。(T092325)

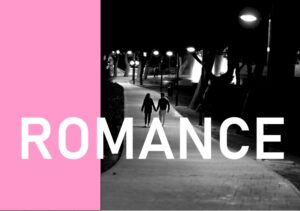
コメント