谷崎潤一郎の小説を市川崑監督が大胆に翻案して映画化した京マチ子主演作品
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、市川崑監督の『鍵』です。谷崎潤一郎が昭和31年に中央公論誌に連載した長編小説を原作として、脚本は監督の市川崑が和田夏十・長谷部慶治とともに大幅に改編して書き上げました。主演の京マチ子は当時「グランプリ女優」として海外で最も知られていましたが、本作も1960年のカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞し、ゴールデングローブ賞でも外国語映画賞を獲得しています。キネマ旬報ベストテンでは第9位にランクインしていて、ちなみに市川崑監督が同じ年に製作した『野火』も第2位に選ばれています。
【ご覧になる前に】永田雅一の海外戦略が奏功してカンヌで賞を受賞しました
観客に向って老化について説明を行った木村は大学病院のインターンとして古美術商の剣持を診察しています。血圧が高いのに強壮剤の注射を打っていることは妻には秘密にしてくれと頼む剣持が帰ると、夫の健康を気にする妻の郁子がやってきて、自分が来たことは内密にとお願いします。木村は剣持の娘敏子と婚約していて、病院の裏口に来た敏子は昨夜木村にすっぽかされたコンサートのチケットを押し付けます。その晩、カラスミを土産に木村が剣持家を訪れると、剣持は仕事があると言って木村と郁子を二人だけにするのでした…。
日本文学を代表する小説家のひとりである谷崎潤一郎は明治19年生まれで、戦前には探偵小説や映画の脚本なども書いていましたが「痴人の愛」で大きな評判を呼び、戦後すぐに「細雪」を完成させて文壇における地位を確立しました。昭和40年に七十九歳で没していますから、「鍵」は晩年期の作品にあたります。海外でも多くの作品が翻訳されて谷崎の存在は国際的なものになっていき、昭和33年以降、ノーベル文学賞候補に何回もリストアップされていたそうです。
大映の永田雅一社長は、争議で東宝を離れていた黒澤明監督が大映で撮った『羅生門』でヴェネツィア国際映画祭金獅子賞を獲得すると、海外市場を意識した映画製作の重要性に気づきます。当時日本製品を外国に買ってもらって外貨を獲得しようという方針が政府から産業界に伝えられていて、政界の動向に敏感だった永田雅一は日本映画での外貨獲得を目論んで、海外で開催される映画祭での賞を狙った作品を作れと大映で号令をかけます。ヨーロッパの映画人たちが日本映画の存在を再認識したこともあり、永田雅一の作戦は見事に当たり、衣笠貞之助監督の『地獄門』がカンヌ国際映画祭グランプリ、溝口健二監督の『雨月物語』『山椒大夫』がヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞を受賞したのでした。
賞を獲得したとはいっても、これらの作品はジャンルとしてはすべて時代劇に属していて、映画のクオリティに対してというよりも日本という極東の異国がもつエキゾティズムに興味をそそられての受賞という側面があったことは否めませんでした。実際にカラーで撮影された『地獄門』は1959年度のアカデミー賞で衣裳デザイン賞(カラー部門)でオスカーを獲得していますから、永田雅一はキモノやゲイシャなどステレオタイプな日本のイメージをうまく活用していたのでもありました。
『羅生門』と『地獄門』に出演していたのが京マチ子で、大阪松竹少女歌劇団から大映に入社して女優となった京マチ子は160cmという長身とグラマラスな肢体を持ち、いわゆる「ヴァンプ女優」として売り出されていました。やがて京マチ子の主演作が海外で賞を獲得すると、日本映画界での呼び名は「グランプリ女優」に変わり、ヨーロッパにおいて京マチ子は日本を代表する女優として認められていきます。特にフランスでは木村恵吾監督の『千姫』なども公開され人気を博したようです。
永田雅一としては、時代劇一辺倒ではない日本映画のクオリティで勝負したいという気持ちがあったのかもしれません。風営法に翻弄される娼婦たちを描いた溝口健二の『赤線地帯』では賞を逸していますから、ノーベル文学賞候補にもあがっている谷崎潤一郎を原作に取り上げて、老人の性欲というややセンセーショナルなテーマを取り上げることによって、海外市場から耳目を集めようとした可能性は否定できないと思います。結果的に市川崑監督の『鍵』はカンヌ国際映画祭でミケランジェロ・アントニオーニ監督の『情事』とともに審査員賞を分け合うという栄誉を獲得したのでした。
【ご覧になった後で】宮川一夫がアグファカラーで撮影した映像が見事でした
いかがでしたか?谷崎潤一郎の原作を読んだことがないので何とも言えませんが、小説は老人とその妻が互いに日記を書いていて、その日記を鍵のかかる引き出しにしまっているのに、妻に日記を盗み読んでほしいと鍵をわざと落とすという設定になっているそうです。日記とはきわめてプライベートな告白文でもあるので、老人と妻がそれぞれ心のうちをしたためるわけですが、相手に読ませたいとか相手が読むとかいう前提条件を加えることによって、自分のために書いたのか相手に読ませるためのものなのかの線引きが曖昧になるという状況が成立します。なので谷崎潤一郎が小説でしか伝えることができない表現方法で書いた作品なのではないかと思われます。
そんな小説をどうやって映画化するかは映画監督やシナリオライターにとっては大きな挑戦だったことでしょう。しかしながら妻に不倫関係となる男をあてがってその嫉妬心から自らの性欲を回復させようという性的表現が当時の国会で取り上げられて社会的問題化し、映画化は一時頓挫してしまったんだとか。その騒動がひと段落したところで谷崎潤一郎が市川崑に映画化権を売って、市川崑が専属契約を交わしていた大映で製作することになったそうです。映画化にあたっては、市川崑は妻の和田夏十と『処刑の部屋』や『炎上』でコンビを組んだ長谷部慶治とともに大幅に原作を改編して、鍵は引き出しのものではなく裏口の鍵に変更し、ラストもブラックコメディ調の終わり方にしてしまいました。谷崎潤一郎はちょっとだけ異議を唱えたそうですが、結果的には市川崑バージョンで映画は完成されることになったのでした。
そんな経緯があるので、映画として見ると中村鴈治郎演じる老人がなぜ妻の郁子と仲代達矢を接近させようとするのか、その意図がはっきりとは伝わってきませんでした。浴室から寝室に運ぶのを手伝わせるのは仲代達矢が医者の立場なら当たり前ですし、妻の裸を撮ったフィルムを現像させた後では特にその写真を受け渡しする場面が出てこないので消化不良のままです。京マチ子演じる郁子も何度も裸で倒れるというのが小説ならともかく映画ではリアル過ぎて、早く救急車を呼んだ方がいいのではないかと心配してしまいますし、そうでなければわざと倒れたふりをしているとしか思えなくなってしまいます。ことほどさように小説では文章で読者に想像させて何が真実かを類推させる効果があるんでしょうけど、映画では直接的な映像を見せてしまうので観客にあれこれ想像させることができなかったのではないでしょうか。
そういう中途半端さのまま終わることができなくなって、最後にはお手伝いの北林谷栄が毒殺したにも関わらず無理心中だと断定されるエンディングを付け足したのかもしれないと邪推してしまいますね。京マチ子の日記の中で木村と娘の三人で暮らしていくという記述に「天国」という言葉があったことが決め手になるように描かれていましたけど、京マチ子が仲代達矢との関係を続けるために娘に結婚させるのだと匂わせることが映画ではできなかったんでしょう。それでブラックコメディ的な終幕が用意されたのかもしれません。
脚本としてはいろいろと疑念が残る出来栄えですが、映像的センスと画面の美しさには本当に圧倒されるくらいでした。本作は大映東京撮影所で作られていまして、当時の大映の技術スタッフの力量の高さが作品として残されたことには映画史的価値があると思います。
市川崑はカッティングにオリジナリティがあり、編集というかショットのつなぎ方に独自のセンスがあると思うのですが、本作ではその特徴はあまり出すことなく映し出される対象のほうに工夫の重きを置いていました。そのひとつが登場人物たちのメイクアップで、京マチ子の切れ上がった眉と叶順子のゲジゲジ眉毛の対照はやりすぎとも思えるくらいでした。また中村鴈治郎と仲代達矢も白とピンクの中間のようなのっぺりした顔面メイクでほとんど表情の変化を見せないようにしていて、全員が内面的な演技ではなく、セリフと行動のみで表現されるような演出がなされていました。この演出法はラストまで一貫していて、毒を飲まされた三人が三人とも悶絶すらすることなく表情を変えずに食卓に倒れ伏すのが黒い笑いを誘う効果につながっていたと思います。
またキャメラマンの宮川一夫による色と影のコントロールが本当に見事で、特に剣持家の室内シークエンスでの光と影の表現は撮影と照明と美術のスタッフが一体となった職人技だなと感心してしまいました。日本家屋なので室内ではあまり外光が入らない設計なわけですが、玄関から廊下、土間に至る間に外の光が漏れているというシチュエーションを作り出していて、人物を移動させることで光と影の中で人物が演技するという舞台設定を映像にしていました。一方で裸の京マチ子が運び込まれる寝室では蛍光灯のような陰影のない一面的な照明の中で平面的に人物を映し出すことで、キャラクターの浅はかさを強調するような表現になっていました。
室内撮影では、京マチ子と叶順子が久しぶりに二人で夕飯を食べる場面があり、こちらは暖色の白熱灯を生かした映像づくりがされていて、特に手前に映った叶順子と奥にいる京マチ子の両方の顔にバッチリピントが合ったショットが出てきたのにはびっくりしました。この照明でパンフォーカスにするためにはかなりの光量が必要ですが、それを前後のショットと全くトーンを変えずに撮影できるのは凄まじい技術の裏付けがないとできないはずです。
ロケーション撮影では剣持家を出た塀沿いのショットにいくつかの見どころがありました。中村鴈治郎とすれ違った京マチ子が耳にイヤリングをつけるところ。シネマスコープの横長画面の中で京マチ子のバストショットの向こう側にこちらを伺う中村鴈治郎が小さくぼやけて映り込んでいます。それを切り返して中村鴈治郎側からのショットになったときに、京マチ子が持った手鏡に光が当たって反射するのは見事な効果がありました。現在であればわざわざ反射させなくてもCGでいくらでも光を加えることは可能ですが、本作ではすべてアナログでやっているわけですから太陽の位置や鏡の角度やキャメラの露出などが完全一致しなければ撮れないショットです。こうしたワンショットも手抜きをしないところに大映東京撮影所の気概が伺えます。
大映のカラー作品はアメリカのイーストマンカラーが採用されていたはずですが、本作はドイツのアグファカラーで撮られています。大映が『地獄門』をカラー映画として製作するために永田雅一は撮影技師をアメリカに派遣して徹底してカラー撮影の技術を研究させ、結果的に採用されたのはイーストマンカラーでした。永田雅一は東洋現像所の五反田工場でカラー専用の現像ラインを組ませて、日本国内でイーストマンカラーで撮影したフィルムを現像してプリントするインフラを作った人ですが、競争させなければ技術革新が続かないという意識もあったんでしょうか。アグファカラーと技術提携した東京現像所を大沢商会・松竹・東宝と共同で昭和31年に立ち上げたのでした。
おそらくアグファカラーの日本導入にあたっては小津安二郎の意向が大きく影響したのではないかと想像されるわけで、小津の最初のカラー作品『彼岸花』は昭和33年9月に公開されています。市川崑は前作『あなたと私の合言葉 さよなら、今日は』をアグファカラーで作っていまして、昭和34年1月公開のこの作品は小津映画のパロディ的な意図を感じさせるものでした。そして昭和34年6月に『鍵』がアグファカラーで製作され、5ヶ月後の11月に小津安二郎は『彼岸花』で若尾文子を使ったお返しとして大映で『浮草』を撮ります。もちろん『浮草』もアグファで撮られいて、キャメラマンは宮川一夫ですから、イーストマンカラーを使うのかアグファにするのかといった選択は、このような映画会社と映画監督の当時の関係に左右されたのではないかと想像されます。
蛇足ですが、本作の翌年に市川崑が宮川一夫を再度キャメラマンに起用して完成させたのが『おとうと』でした。宮川一夫が銀残しという手法でくすんだ画面を作り出したことで有名ですが、『おとうと』もアグファカラーで撮影されています。『鍵』の撮影が『おとうと』の映像美につながったことは間違いないところでしょうね。(A071925)

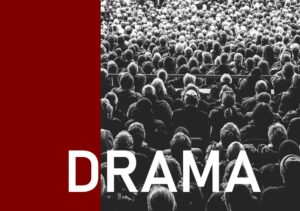
コメント