 日本映画
日本映画 エノケンのホームラン王(昭和23年)
昭和21年には8チームによるリーグ戦を再開したプロ野球の中でも一番の人気球団はジャイアンツで、本作はジャイアンツフリークの榎本健一がジャイアンツに入団して選手たちの信頼を獲得していくという野球ファンタジーになっています。
 日本映画
日本映画 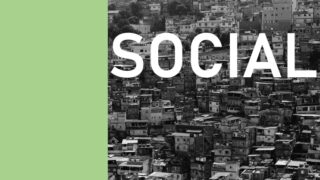 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  昭和二十年代
昭和二十年代 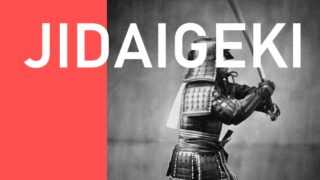 日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画  日本映画
日本映画