ジャン・マレーと岸恵子共演の日仏合作映画はフランスで大ヒットしました
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、イヴ・シャンピ監督の『忘れえぬ慕情』です。松竹がフランスのパテシネマなど複数の映画製作会社と組んだ日仏合作映画で、脚本には松竹から松山善三が参加し、フランスのイヴ・シャンピが監督をつとめました。主演の岸恵子は本作の撮影後にイヴ・シャンピと結婚することになり、フランスでは公開とともに大ヒットを記録。パリに日本ブームが到来するほどの人気だったそうです。
【ご覧になる前に】『亡命記』を見たシャンピ監督が岸恵子に出演をオファー
長崎の造船所で行われたタンカーの進水式では、フランス人技師マルサックが乃里子に手を振っています。堀技師長を介して知り合った二人は愛し合うようになっていて、呉服屋を営む乃里子にフランス語を教えていたスイス系ドイツ人リッテルの屋敷の離れにマルサックは住まいを移します。乃里子の妹の結婚式に参列する約束をしたマルサックのもとにやってきたのは女流作家のフランソワーズ。彼女はかつての恋人マルサックとよりを戻そうと長崎に駆けつけたのでした…。
1921年生まれで当時三十五歳のイヴ・シャンピは、医科大学生から地下運動に入ってノルマンディ上陸作戦にも軍医として加わった経験の持ち主。司令部から渡された16ミリカメラで解放されたパリのシャンゼリゼ大通りを凱旋するド・ゴール大統領を撮影し、そのフィルムは『栄光の仲間たち』というドキュメンタリー映画として公開されてヒット作になりました。世界的なピアニストのマルセル・シャンピと同じく世界的なヴァイオリニストのイヴォンヌ・アストリュックを両親に持つ第二次大戦の英雄イヴ・シャンピは映画監督の道を歩むことになったのでした。
松竹で映画女優としてデビューした岸恵子は、『君の名は』でトップスターになっていましたが、会社から与えられるお仕着せの作品には満足していませんでした。昭和29年に久我美子・有馬稲子と三人で「文芸プロダクションにんじんくらぶ」を設立し、五社協定に負けることなく自分で出演作を選ぶ権利を勝ち取ります。そもそも松竹は岸恵子と正式な専属契約を交わしていなかったそうですから、当時は映画会社と俳優の雇用関係とか出演契約などは結構いい加減だったようですね。
野村芳太郎監督の『亡命記』で令夫人から日雇い労働者に落ちぶれるまでを演じた岸恵子は、1955年にシンガポールで開催された東南アジア映画祭で最優秀主演女優賞を受賞しました。この授賞式に出席していたのがデヴィッド・リーン監督で、次回作として企画されていた「風は知らない」の主人公に岸恵子がぴったりということになって、帰国した岸恵子を追ってデヴィッド・リーン自ら日本で出演交渉をしたんだそうです。
英語の特訓をするためにロンドンに滞在していた岸恵子に届いた知らせは「風は知らない」の製作中止を伝えるものでした。プロデューサーのアレクサンダー・コルダが急逝したため、デヴィッド・リーンは岸恵子主演映画を諦めなければならなくなったのです。衝撃に打ちのめされていた岸恵子を救ったのがイヴ・シャンピで、『亡命記』を見ていたシャンピは松竹を通じて「長崎の台風」なる映画への出演をオファーしたのでした。シャンピが監督した『悪の決算』を二度見ていたという岸恵子は、「長崎の台風」に出演することを決め、急遽フランス語を習得するためにパリに移動することになりました。
結果的には日本の文化や習慣を尊重して撮影現場を統率するイヴ・シャンピに惹かれて岸恵子は結婚することになるわけですから、岸恵子にとって『亡命記』は運命の一作だったといえるでしょう。女優最後の仕事という意気込みで臨んだ『雪国』の撮影が終了すると、岸恵子は小津安二郎の『東京暮色』や今井正の『夜の鼓』の出演依頼を蹴ってフランスに旅立っていきました(二作とも「にんじんくらぶ」の僚友だった有馬稲子が代役をつとめることになります)。
ちなみにデヴィッド・リーンはよほど岸恵子を気に入ったのか、『戦場にかける橋』に岸恵子のための役を書いて再度出演依頼をしたそうです。その当時『雪国』を撮影中の岸恵子は、『雪国』で女優生活に終止符を打つ決心をしていたためオファーを辞退。ウィリアム・ホールデンまで岸恵子のもとに交渉に送り込まれたのですが、結局岸恵子のための役は削除されたということらしいです。
【ご覧になった後で】通俗的メロドラマですが台風の特撮は特筆ものでした
いかがでしたか?日仏合作なのでセリフも日本語とフランス語で話されますし、ときには英語もはさまってくるので、「フジヤマ・ゲイシャ」のようなステレオタイプが出てくるよくあるヘンテコな日本が描かれているのかと思いきや、フランス語のセリフの後にはごく普通の日本の日常会話がきちんと録音されていて、純粋な日本映画と外国が作ったヘンな日本がごちゃ混ぜになったような妙な作品に仕上がっていました。逆に言えばそのごちゃ混ぜ感は岸恵子が恋したイヴ・シャンピ監督のフェアな製作態度が反映されたためだったのではないかと思われ、台風襲来に備える山村聰が工場の配下に「三階の窓をよく見れくれよ」なんて指示を出す場面などはとても外人監督が指導したものとは思えないほど日本映画っぽさが垣間見えるのでした。
イヴ・シャンピらが書いた共同脚本には松竹から松山善三が参加していて、当時まだ助監督だった松山善三にとっては高峰秀子と結婚した翌年の仕事にあたります。たぶん日本語のセリフは全部松山善三が書いたんでしょうし、まあイヴ・シャンピから見ても日本人の出演者がどこでどんなセリフを言っているのかよくわからなかったでしょうから、日本語のセリフが自然に聞こえるのは日本のスタッフがある程度信頼されていた証左なのかもしれません。
本作はイーストマンカラーで撮影されていて、キャメラを任されたアンリ・アルカンはルネ・クレマンの『鉄路の闘い』以降、ジャン・コクトーの『美女と野獣』、マルセル・カルネの『愛人ジュリエット』、ウィリアム・ワイラーの『ローマの休日』など映画史に残る名作を撮影した人でした。松竹は日本映画初のカラー映画『カルメン故郷に帰る』を製作していますが、国産のフジカラーはピーカンの外光での撮影が絶対条件だったため、本作ではスタジオ撮影にも対応できて比較的安価なイーストマンカラーが採用されています。もっとも豪華絢爛な着物をカラー映像で映した大映の『地獄門』でイーストマンカラーで作られていましたから、カンヌ映画祭グランプリとアカデミー賞名誉賞(外国語映画賞)を獲得したことも相まって、カラー映画の先駆者だったはずの松竹もフジカラーを捨てざるを得なかったと思われます。
そんなわけで日仏合作の効果もそれなりに感じられ、イーストマンカラーの発色も綺麗な作品ではあるものの、岸恵子と愛し合っている風のジャン・マレーが、昔の恋人のダニエル・ダリューが現れるとすぐによりを戻してしまうという軽薄さというかフランス人っぽさにはなんとも呆れてしまいますよね。ダニエル・ダリューも当時のフランス人なら岸恵子ごときをライバル視しないだろうと思うのですが、真剣にタメを張るような勢いで、台風なのにジャン・マレーがいる造船所に来てしまうのもなんとも解せない展開でした。さらにはそこからなぜか仕事に戻らないジャン・マレーと百貨店の店内に避難して、さらにはジャン・マレーが台風の暴風で木造家屋が次々に倒壊する中をわざわざ岸恵子がいる呉服屋まで走っていくのもいかにも不自然ですし、飛ばされた戸板があたった程度にしか見えない岸恵子が死んでしまうのも無理筋でご都合主義っぽさがぬぐえませんでした。
しかしながらこの台風襲来シークエンスの特撮はものすごく良い出来栄えで、その完成度だけは特筆ものでしたね。特殊技術を担当したのは川上景司で、東宝に入社して円谷英二課長率いる特殊技術課に配属されてから特技専門の道を歩んだ人です。『ハワイ・マレー沖海戦』などの特撮を駆使した戦意高揚映画を東宝が得意とするのを見ていた松竹の城戸四郎が、自社の特撮部門を強化すべく高給で東宝から引き抜いたが川上景司でした。台風でうねる海面の表現や強風でなぎ倒される家屋のリアルさなどは、東宝特撮映画に比べても決して引けを取らず、本作の一番の見どころになっていました。ちなみに川上景司は本作で日本映画技術賞の特殊技術賞を受賞しています。
当時の長崎には台風が来たことがなく、原題の「長崎の台風」は日本版では『忘れえぬ慕情』というロマンチックなタイトルに変更されてしまいました。しかし風が強くなり急に雨が降り出す描写は台風接近の様子を端的に表現していましたし、暴風雨から身を守るために百貨店の店内に避難した人々の様子は長崎に落とされた原爆のイメージを想起させるメタファー的な描写になっていました。さらには台風一過の晴天のもとで瓦礫を片づけて復興に向う町の様子をクレーンでとらえた移動ショットは本作の白眉とも言える感動的かつ躍動的な映像になっていたと思います。
というわけでそれほど感心するような作品ではありませんでしたが、日本映画史的に見ると岸恵子の人生を大きく変えた作品として重要なポジションに位置しますし、日仏合作映画としてヘンテコにならずそれなりの出来栄えになったのはイヴ・シャンピの功績だったと思われます。言い忘れましたが、「ゴールドフィンガー」ことゲルト・フレーベが浴衣の似合う親日家を演じていたことや、木下忠司の金属系打楽器をフィーチャーした音楽も本作の雰囲気づくりに貢献していたことも印象的でした。(U111625)

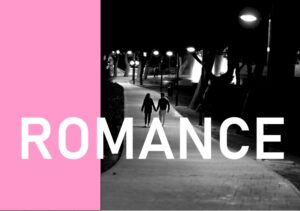
コメント