藤純子が矢野竜子を演じる緋牡丹博徒シリーズ第七弾は鶴田浩二が相手役です
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、加藤泰監督の『緋牡丹博徒 お命戴きます』です。藤純子が「緋牡丹のお竜」こと矢野竜子を演じる『緋牡丹博徒』が昭和43年に公開されてヒットを飛ばすと、東映はすぐにシリーズ化を企画しました。本作はその第七作にあたり、鶴田浩二が第五作『緋牡丹博徒 鉄火場列伝』に続いてお竜さんの相手役をつとめています。藤純子は本作公開翌年の昭和47年に歌舞伎役者四代目尾上菊之助と結婚して引退しますので、「緋牡丹博徒シリーズ」も次作『緋牡丹博徒 仁義通します』で打ち切りとなりました。
【ご覧になる前に】加藤泰の監督は『花札勝負』『お竜参上』に続いて三作目
上州伊香保を渡世修行中の矢野竜子は久保田組が闇討ちしようとした安二郎を救います。宿場の賭場でイカサマを見破った竜子は久保田組に囲まれますが、その場を収めたのが熊谷結城組の菊太郎。妻に先立たれ幼子の世話をする結城は、国策で建設された軍需工場から出る煙と排水で苦しむ農民たちに代わり、工場に談判に行きますが、工場と癒着した軍人にメッタ打ちされてしまいます。勧進賭博のため九州から舞い戻ったお竜は、結城が叔父貴と慕う冨岡組が不穏な動きをしていることに気づくのでしたが…。
本作は昭和46年6月に東映系劇場で公開されていまして、翌年3月の『関東緋桜一家』で藤純子は映画界を引退することになります。歌舞伎役者の尾上菊之助との結婚と同時に引退した藤純子は当時二十六歳。東映としてはヒット作を飛ばす女優を引退させるのは惜しいと考えたはずですが、藤純子が尾上菊之助と出会ったのは昭和41年にNHKで放映された大河ドラマ「源義経」でのこと。義経を演じた菊之助と静御前を演じた藤純子の出会いは藤純子が二十一歳のときです。五年以上の交際期間を経てやっとのことで結婚することができた二人にとっては東映には十分恩返ししたという思いだったでしょう。
TVドラマで注目された藤純子は、東映では相変わらず東映京都のヤクザ映画や東映東京で製作された戦争ものの端役といった出演しかなく、初めての主演作品は昭和43年2月公開の『尼寺(秘)物語』という中島貞夫監督のキワモノでした。当時東映の常務だった岡田茂が女性を主人公にしたヤクザ映画を企画して、藤純子が抜擢されたのが『緋牡丹博徒』。緋牡丹のお竜を演じた藤純子は一躍東映を代表する女優となったため、昭和44年には「緋牡丹博徒シリーズ」三作を含む12本の映画に出演する大車輪の働きを強いられたのでした。
第三作『花札勝負』で「緋牡丹博徒シリーズ」の初メガホンをとったのが加藤泰。加藤泰はシリーズ最高傑作の誉れが高い第六作『お竜参上』も監督していますから、本作はシリーズ三本目の監督作品になります。脚本は加藤泰に加えて、第二作『一宿一飯』を監督した鈴木則文、『昭和残侠伝 死んで貰います』を書いた大和久守正がクレジットされていて、キャメラマンは『関東緋桜一家』を撮ることになるわし尾元也がつとめています。
【ご覧になった後で】正対横イチで撮ったローアングルの構図が見どころです
いかがでしたか?渡世の修行旅の途中で知り合った義侠心に富む地元ヤクザを緋牡丹のお竜が助けるという鉄板ストーリーは安心して見ていられますし、なにしろ藤純子の美しさは脂がのった最盛期にあり、藤純子の顔と所作を見るだけでもそれなりに満足してしまうという作品でした。意外と早く死んでしまう鶴田浩二もやや抑え気味ながら相変わらずの重厚感がありましたし、河津清三郎の悪役ぶりも文句なしの憎まれっぷりで、役者がハマるとそれだけで成立してしまうのがこの当時の東映ヤクザ映画のパターンだったんだなと思わされました。
本作の見どころはストーリー展開や配役などではなく、加藤泰の手による映像の作り方にあったことは間違いないでしょう。まるで演劇の舞台を見ているような正対横イチの構図は決して斜めからの視点になることはなく、キャメラは被写体に向って必ず直角に正対するようにセットされます。そのうえで室内シーンでは畳が敷かれている床スレスレのローアングルから撮られるので、観客にとっては客席から演劇の舞台を見るのと同じ視点からスクリーンの映像を見ることになります。そのうえで加藤泰は横長スクリーンに投影される画面いっぱいを使って、登場人物全員の配置を決め動きを決め段取り通りに演技させていきます。このコントロール力が凄くて、いくつかの長回しショットは非常に完成度が高いものになっていました。
たとえば鶴田浩二演じる結城の棺を前にした結城一家の室内シーン。上岡紀美子演じる結城の妹が三代目に指名された名和宏に向って結婚は待ってくれと頼み、農家の沢淑子が売られそうになった娘を救ってくれたと泣き、組員たちが冨岡一家に殴り込みをかけようとする流れを、藤純子が一喝して収める場面。この芝居をひたすら横からフィックスで長回しで撮っているのですから、俳優たちは舞台のように真剣勝負の演技をしなければなりません。しかも舞台では考えられないくらいの大人数が画面の中に押し込まれるように配置されていて、それぞれがキャラクターになりきった動きをするのです。
待田京介演じる常五郎がお竜のために棺桶(時代背景に合わせて屈葬のための早桶で作られています)の蓋をズラしてあげる動作も、この長回しショットの中に巧みに計算して織り込まれていました。そして最後には照明が落とされて藤純子だけにスポットライトが当たり、鶴田浩二の意思を藤純子が引き継ぐという芝居が完成されるのです。照明もですけど、音声は同時録音でしか成立しないので音響さんの仕事はかなりの難易度だったのではないでしょうか。マイクをどこに下げるかなど本当に細かな職人技がキャストもスタッフも全員要求される場面でした。
この正対横イチ長回しショットはクライマックスの葬式の場面でも出てきます。河津清三郎が焼香しようとするのを「その焼香、待ちんしゃい」と藤純子が止め、真っ白な背景から藤純子が入って来る後のショット。ここで河津清三郎が黒幕であると名和宏が告白して大乱闘になりまして、普通のヤクザ映画なら短いショットの連打で派手な斬り合いアクションシーンに移行するはずです。ところが加藤泰はこの横イチフィックスのままアクションを進めるんですよね。藤純子が画面左のほうに下がり、右手から冨岡組の組員たちをなだれ込ませ、画面手前が男衆たちで埋め尽くされ、ロングショットはいつのまにか大勢の取っ組み合いのミディアムショットに変わります。人物の動きで画面構成を変化させるので見ていて飽きることはありませんでした。
このあとは藤純子が河津清三郎を追い詰めて工場の排水にまみれさせて一巻の終わりとなる展開。葬儀会場から草むらを経て田んぼの排水という場面転換が非常に短いショットの積み重ねで描かれます。長回しショットのリアルさから一気にイメージ重視の抽象的な演出に変化するわけで、こういう変幻自在さが加藤泰の真骨頂なのかもしれません。長回しショットのお話だけに偏ってしまいましたが、超クローズアップを様々に構図を変えてインサートするのもメリハリが効いていて非常に効果的でしたし、インサートショットもどこかから覗くかのように画面半分が物陰で真っ黒だったりするのが、本作をプロフェッショナルの職人による手仕事っぽく見せていました。
若山富三郎によるおなじみのコメディーリリーフぶりや陸軍大臣役で出てくる石山健二郎のふんどし姿は本作の余興のような位置づけでしょうか。首吊り偽装される内田朝雄は相変わらずの役どころでしたけど、ピストル自殺する大木実は煮ても焼いても食えないという感じがしてしまい、ミスキャストとしか思えませんでした。
本作のようにストーリーもキャラクターも観客の予想通りに進むという映画の場合は、加藤泰監督のような映画の見せ方で工夫していかないと、あまりにもわかりやす過ぎてつまらないものになってしまうでしょう。昭和46年当時は新しい企画や新しい脚本などは望むべくもなく、おなじみのお話をおなじみの俳優で見せる作品が週替わりで公開されていたわけです。わざわざ映画館に足を運ぶ観客も大きく減ってしまい大映が倒産したという時代に、本作のような監督の手仕事的作品が残されたのは、日本映画史における徒花であったような気がしてなりませんね。(V072625)

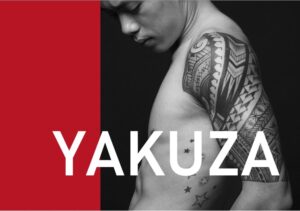
コメント