会津若松を舞台にして幼馴染の5人の若者たちの青春が交錯する友情物語です
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、木下恵介監督の『惜春鳥』です。「せきしゅんちょう」と読ませる題名は、主人公の若者たちが青春時代に別れを告げて大人になっていくことへの哀切な思いを表現していると思われます。会津若松が舞台になっていて、若くして死んでいった白虎隊の青年たちに現在の自分の境遇を重ねるという設定が本作の基本的なモチーフになっており、木下恵介監督作品の中でもとりわけ男同士の友情がフィーチャーされた作品です。
【ご覧になる前に】本作で十朱幸代がデビュー、もちろん脚本も木下恵介です
磐梯山が近づく汽車に乗った学生服の岩垣は車内で友人牧田の叔父から声をかけられます。若松に一時帰郷する岩垣は、町の有力者鬼塚の支援で東京の大学に進学したのですが、牧田の叔父は鬼塚が囲う芸者と駆け落ちをした末に身体を壊し、若松に戻るところでした。岩垣は友人峰村の実家がやっている旅館の一室に逗留することになり、風呂に入っていると足が不自由な馬杉も訪ねてきました。三人は牧田と手代木を呼び出して、白虎隊の青年19人が自刃した飯森山に登り、かつて披露したことがある剣舞を舞うのでしたが…。
昭和20年代後半から30年代半ばまで、松竹の木下恵介は東宝の黒澤明と並んで日本映画界を代表する映画監督として、次々に新作を発表していました。両人ともに監督をするだけではなく脚本も自分で書いていましたが、複数人のチーム制で脚本を練り上げた黒澤明と違って、木下恵介はいつも他人の手を借りずに単独で脚本を書き上げる人でした。昭和29年に『二十四の瞳』を大ヒットさせた後の数年間は木下恵介のキャリアの絶頂期にあたり、年二本の作品をコンスタンスに発表していて、『野菊の如き君なりき』『夕やけ雲』『喜びも悲しみも幾歳月』『楢山節考』と日本映画史に残る名作を連打していました。本作は『笛吹川』の前年に公開されていて、一連の傑作の中では木下恵介のプライベートな感情面が押し出されたヴィヴィッドな仕上がりになっています。
本作の舞台となっている「若松」は、若松市が周辺の七村を編入して昭和30年に会津若松市と変更したので、地元の人たちとしては若松の呼び名が定着していたものと思われます。その会津若松市の北東郊外に位置するのが標高314mの飯盛山。新政府軍と幕府軍が戦った戊辰戦争は、幕府側についた会津藩の処遇を巡って会津戦争の局面を迎えます。新政府軍と戦うために会津藩が十代の武家男子を集めて編成したのが白虎隊で、中には十三歳の少年もいたと言われています。最終的に会津藩は新政府軍に敗れ降伏を余儀なくされるのですが、白虎隊の若者19人は敵に捕まる前に飯盛山で自決して果てました。飯盛山に白虎隊士の墓所が建立されたのは二十三回忌にあたる明治23年のことでした。
若松を故郷とする若者たちを演じるのは、津川雅彦、川津祐介、小坂一也、石浜朗、山本豊三の五人。津川雅彦は昭和31年の『狂った果実』で石原裕次郎の弟役を演じて注目され、昭和33年に日活から松竹に移籍したばかりの頃。川津祐介は松竹でデビューして間もない時期でしたが、翌年大島渚監督の『青春残酷物語』に主演してブレイクすることになります。小坂一也はNHK紅白歌合戦にも出演するなど歌手としての地位を確立してから映画界に進出して、前年に『この天の虹』で木下作品に出演したところでした。山本豊三は『酔いどれ天使』でヤクザの親分をやった山本礼三郎の息子で、松竹では小坂一也・三上真一郎とともに「松竹三代目三羽烏」として売り出されたのですが、あまり大成しなかったようです。
木下恵介の『少年期』でオーディションの末に十六歳でデビューしたのが石浜朗。その初々しさに注目した黒澤明が自作に出演をオファーしたのですが、ちょうど大学受験にあたったため石浜朗はその話を断ったそうです。黒澤明は『七人の侍』の勝四郎役に石浜朗を使おうと考え、結局木村功が演じることになりました。石浜朗は勝四郎役を受けていたら別の人生を歩んだかもしれないと後になって振り返っています。
そして本作で映画界デビューを果たしたのが十朱幸代。戦前はテアトル・コメディの演劇人として活躍していた十朱久雄は、戦後になるとラジオ出演を契機に映画にも出演するようになり、松竹版『自由学校』以降、多くの映画監督に重用された人でした。娘の十朱幸代は幼い頃から女優志望だったらしく、モデルをしていた中学生のころにNHKにスカウトされて「バス通り裏」で芸能界に入りました。その流れで映画にも出ることになり、本作は十六歳での映画デビュー作にあたります(日活の『警察日記』にも出演記録があるので子役としては出演済みだったかもしれません)。昭和38年に日活に移籍しているのですが、どうやら十朱幸代は小坂一也と同姓して事実婚状態にあったそうですから、そんな事情も移籍の背景にあったのかもしれません。
【ご覧になった後で】複雑な展開ながら俳優たちの個性が活かされていました
いかがでしたか?冒頭で佐田啓二と川津祐介が車内で交わす会話から二人が置かれている苦境が伺われる展開になっていて、ワンシーンワンショットの長回しのすばらしさとともに緊張度を強いるような導入部でした。案の定、若松の町に入ると次々に新しい人物が登場してきて、彼ら彼女らの人間関係を追いかけるのにかなり苦労させられます。旅館の跡取り息子の小坂一也や足を悪くして会津塗の家業を継ぐ山本豊三はまだわかりやすいのですが、佐田啓二の甥にあたる津川雅彦の家族関係は複雑過ぎてあまりよく理解できないままに映画が進行していきます。バーを経営している母親の藤間紫が伴淳三郎の妾なのか、津川雅彦の父親は誰で、佐田啓二は父方・母方どちらの叔父なのか、などは結局よくわかりませんでした。また石浜朗の家はかつての士族ということでしたけど、生活が貧しいという様子は笠智衆が一度登場するだけなので読み取るのが難しかったです。
そんな難しい脚本の中でもなんとなく話の筋を追えたのは、5人の若者を演じる俳優たちの個性が際立っていたからでしょう。秘密の影を抱える川津祐介、厭世的ながら叔父想いの津川雅彦、屈折しながらも純粋無垢な山本豊三、のんびりしたいい奴風の小坂一也。その中でも存在感が目立ったのは石浜朗で、友人の恋人と見合いをさせられる立場や労働闘争に加わる被雇用者としての側面、裕福な娘と一緒になることへの期待など複雑なシチュエーションを嫌味なく卑屈にならずに演じきっていたのは見事でした。石浜朗の手代木がイヤな奴に見えてしまったら、本作のテーマは友情関係の崩壊だけで終わっていたことでしょう。ラストで飯盛山の高台からいっしょになって降りてくる4人が川津祐介の赤いマフラーを手渡したり捨てたりしながら、最終的には拾って車に乗り込むロングショットは、5人の若者の友情が世間の荒波の中でもこれから永く続くであろうことを暗示しているのではないでしょうか。
映画評論家の佐藤忠男が指摘している通り、本作には木下恵介のホモセクシュアル志向が垣間見えます。若松に帰ってきた岩垣が旧友と再会する場面では、川津祐介は小坂一也の手をしっかりと握りしめますし、その二人が入浴している浴場に入ってきた山本豊三は服を着たまま裸の川津祐介と抱擁します。このような男性同士の身体的な接触は『夕やけ雲』で橋の欄干に腰かけながら足をからませた主人公たちに似ていて、完全なゲイまでは行かないものの自分自身の性的志向・性自認が明確でない「クィア」であることを想起させます。
とは言え、本作にそのような気配が感じられるのはこうした導入部だけであって、その後は特段ホモセクシュアルやクィアな感じが出てくる場面はありませんでした。映画評論家がある視点で作品を論ずるのは観客としては参考程度にとどめておいて、映画自体を純粋に楽しむほうがいいように思います。足が不自由な山本豊三は足のために女性との恋愛をあきらめていて、だから男性に目が行くのだという見方もあるそうですが、それはすなわち身体障碍者への偏見であり尊厳を損なうものにほかなりません。あまり無駄な深読みは必要ないのではないでしょうか。
5人の個性が光っているだけに佐田啓二と有馬稲子のサブストーリーが霞んでしまうようでしたが、有馬稲子は本作では演技の巧さが光っていて、特に月光に照らされた中で剣舞を舞うロングショットは本作屈指の名場面でした。ワイドスクリーンのカラー作品なのに、このショットだけは光と影を強調した青白いモノクローム的な画調で表現されていて、しかも二人の心中はこのショットのみで暗示されています。キャメラマンはいつもの楠田浩之ですが、木下恵介と楠田浩之のコンビは本当にこのようなロングショットの扱いがうまくて、木下作品の真髄が込められているように感じられました。(U051225)

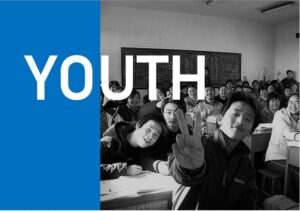
コメント