デヴィッド・リーンが『アラビアのロレンス』に続いて監督した文芸大作です
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、デヴィッド・リーン監督の『ドクトル・ジバゴ』です。デヴィッド・リーンは『アラビアのロレンス』で1962年のアカデミー賞作品賞・監督賞を獲得しましたが、本作はそれに続く文芸大作で、製作が長期間に及んだため1965年に公開されました。公開当初は批評家から酷評を浴び、興行収入も冴えませんでしたが、モーリス・ジャールの主題曲「ラーラのテーマ」がヒットするとともに映画の評判も上がり、同年の全米興行収入では『サウンド・オブ・ミュージック』に次いで第二位となりました。日本では翌年に公開され、キネマ旬報ベストテン外国映画部門で第九位に選ばれています。
【ご覧になる前に】ノーベル賞を辞退したパステルナークの小説の映画化です
巨大なダム現場から戻ってくる労働者たちを眺めるソ連軍人は、ひとりの女性を呼び止めます。トーニャがイエブグラフ将軍から見せられたのはユーリ・ジバゴの詩集に掲載されたラーラという女性の顔。将軍は腹違いの弟ユーリが母親を亡くし、叔父夫婦に引き取られたときのことを語り始めます。医学部を卒業し臨床医を目指す決意をしたユーリは、ある晩「インターナショナル」を歌いながら行進する学生たちを目撃します。その中には眼鏡姿の学生パーシャがいて、その恋人で服飾店の娘ラーラは、母親の愛人であるコマロフスキーと二人でパーティに行くことになったのでした…。
ソ連の作家ボリス・パステルナークが書いた小説「ドクトル・ジバゴ」は1957年にイタリアで出版されました。というのもロシア革命について批判的な内容だったためソ連国内では発表できなかったのでしたが、翌年には18ヶ国で出版され、さらにはノーベル文学賞がパステルナークに授与されることが決まりました。しかしソ連共産党当局がパステルナークに作家同盟から除名し追放すると宣言したため、亡命か辞退かを迫れらたパステルナークはやむなくノーベル賞辞退を選ばざるを得なくなりました。ソ連国内での出版が許可されたのは、ゴルバチョフによってペレストロイカが推進された1988年のことでした。
小説の映画化権は複数のプロデューサーやスタジオが獲得に動き、結果的には最初にイタリアで出版されたことが影響したのかカルロ・ポンティが1963年に取得します。ポンティは『アラビアのロレンス』に匹敵する大作にしようと、デヴィッド・リーンをはじめ『アラビアのロレンス』のスタッフを集結させました。結果的に脚本ロバート・ボルト、撮影フレディ・ヤング、音楽モーリス・ジャール、美術ジョン・ボックスらが『アラビアのロレンス』の砂漠から打って変わってロシアの大雪原を舞台にした本作に取り組みことになったのです。
キャメラマンは当初ニコラス・ローグが起用されていたのですが、デヴィッド・リーンと意見が食い違い降板させられたそうです。フレディ・ヤングは『アラビアのロレンス』の砂漠の撮影で疲労困憊させられた経験から迷った末にニコラス・ローグの後任を引き受けることに同意しました。またモーリス・ジャールは何度もデヴィッド・リーンに作曲のやり直しをさせられ、恋人と休暇を楽しんでこいとアドバイスされ、リラックスした状態であの名曲「ラーラのテーマ」を生み出しました。
結果的には、これら再集結したスタッフはみんな1965年度のアカデミー賞でオスカーを獲得しています。ロバート・ボルトが脚色賞、フレディ・ヤングが撮影(カラー)賞、モーリス・ジャールが作曲賞、ジョン・ボックスらが美術(カラー)賞を受賞し、さらにはフィリス・ダルトンが衣裳デザイン(カラー)賞を獲っていますので、合計5部門を受賞しました。1965年は『サウンド・オブ・ミュージック』が出た年度でもあり作品賞と監督賞は持っていかれましたが、強力な競争相手がある中での5部門受賞は快挙だったと思われます。
主演は『アラビアのロレンス』で鮮烈なデビューを飾ったオマー・シャリフと『ダーリング』でアカデミー賞主演女優賞を受賞することになるジュリー・クリスティ。二人とも本作で大スターの地位を不動のものにしたと言っていいでしょう。アレック・ギネスはデヴィッド・リーンと演出をめぐって口論になったといいますし、ジェラルディン・チャップリンは雑誌でモデルをしていたのをデヴィッド・リーンに見い出され、偉大なるチャップリンの娘でありながら本作で本格的に映画デビューを果たしました。
カルロ・ポンティの意気込みとは逆にMGMはやや腰が引けていたらしく、大画面の70mmフォーマットでは予算がかかり過ぎるということで、本作は35mmパナビジョンで撮影されました。MGMは『ベン・ハー』を70mmで製作して莫大なコストを世界的大ヒットで回収した経験があったものの、その後の大作路線(『キング・オブ・キングス』『戦艦バウンティ号の叛乱』など)が悉く失敗に終わり、1963年以降70mmには手を出さなくなっていたのです。結果的に本作は35mmから引き伸ばされた70mmプリントで上映されることになりました。
【ご覧になった後で】3時間17分の長尺を感じさせない叙事詩的恋愛物語です
いかがでしたか?序曲が流れ、途中で休憩をはさむ古典的な超大作フォーマットで作られていて、上映時間3時間17分の長尺を感じさせませんでした。ロシア革命前夜からソ連共産党支配下のスターリン時代までをユーリとラーラの恋愛を主軸に語っていく叙事詩的大河ロマンス仕立てで、歴史に翻弄されていく多くの登場人物を俳優たちが見事に演じ切っていました。それをフレディ・ヤングのキャメラとジョン・ボックスのプロダクションデザインで立体化し、モーリス・ジャールの音楽が登場人物の感情表現に寄与していて、キャストとスタッフが一体となって本作の魅力が組み上げられていたのではないでしょうか。
フレディ・ヤングのキャメラはところどころに素晴らしいショットが散りばめられていて、大雪原の中をウラル山脈目指して走る貨物列車の前車両を真横からとらえた超ロングショットは朝の光の中で神々しいように感じられました。また馬に乗ったユーリがたたずむ左右対称の森の中の一本道のショット。ラーラに別れを告げてうなだれるユーリがいきなりが白衛軍に捕縛されるという、運命が急転直下していくほんの一瞬の隙間というかピリオドというか時間が凍ったような感じが伝わってきました。そのほかにもベリキノの別荘に向う馬車の周りを仔馬が飛び跳ねるシーンの多幸感、別荘の窓の氷の結晶が融けて春が来ることを表現した暖かさ、氷の宮殿から橇でラーラが去っていくシーンの哀切な感じなど忘れられない映像がたくさんありましたね。
これらの映像を支えていたのはジョン・ボックスの美術で、クレジットではプロダクション・デザイナーですから俳優以外の映像デザインはすべてジョン・ボックスがコントロールしていたものと思われます。学生たちが夜に行進する街やラーラの実家である服飾店の複雑な構造(ここではユーリがラーラとコマロフスキーの不貞関係に気づくガラスの仕切りが効果的でした)、革命後にすっかり荒らされたグロムイコ邸のすさんだ感じ(ラルフ・リチャードソンは『アンナ・カレニナ』のカレーニンというより『落ちた偶像』のベインズを思い出させる好演でした)、神秘的で静謐な氷の宮殿などなど、どれもジョン・ボックスのセンスが生み出したセットデザインでした。
パステルナークの原作が出版禁止にされていたくらいなので、当然ソ連国内での撮影が許されるはずもなく、多くの場面がスペインで撮影されました。インターナショナルの行進場面の撮影は、近所の人たちがフランコ政権が打倒されたと勘違いして警察隊が撮影を中止しにきたそうですし、気温30度なのに凍った湖を突撃する場面を撮影しなければならず川底に鉄の板を敷いてその上を人口雪で固めたりという苦労があったんだとか。氷の宮殿もすべてワックスを固めて作られていたようです。
撮影や美術だけでなく、本作はキャスティングが成功していて、オマー・シャリフが演じたからこそユーリが一貫して篤実な人物に見えましたし、ジュリー・クリスティだからユーリとパーシャとコマロフスキーの間で翻弄されるヒロインを演じられたのだと思います。一説によるとプロデューサーのカルロ・ポンティはラーラ役に妻のソフィア・ローレンを起用するようデヴィッド・リーンに進言したそうですが、背が高すぎるのひと言で全否定されました。またラーラ役のオファーを断ったジェーン・フォンダは後に受けなかったことを非常に後悔していると語っています。
配役ではユーリ役はピーター・オトゥール、トーニャ役はオードリー・ヘプバーン(『マイ・フェア・レディ』のイライザがトーニャのような脇役を受けるはずないですが)、コマロフスキー役はマーロン・ブランドあるいはジェームズ・メイソンを想定していたようです。オマー・シャリフも当初はパーシャ役だと言われていて、主役をオファーされて大変驚いたんだとか。またヨーロッパの俳優たちばかりの中で、ロッド・スタイガーは唯一のアメリカ人だったので、非常に緊張して現場の撮影に臨みました。もちろんそのときは撮影が一年間超に及ぶとは考えてもいなかったんでしょうけど。
というわけで叙事詩的大河ロマンスの傑作と言いたいところですが、長編小説を映画化するときによくある傾向としてどうしてもストーリーや人物描写を省略してしまうという欠点が本作のあちらこちらに出ていたようにも思われます。まずアレック・ギネスの義兄の存在。映画の冒頭でアレック・ギネス演じる将軍が自分の姪、すなわち弟ユーリの娘を探していることがわかりますが、回想になった途端にユーリが母親を亡くして孤児になった場面になります。そのまま叔父の家で医学生に成長するので、アレック・ギネスの義兄の存在は革命後にユーリが叔父宅に帰還して義兄の訪問を受けるまでほとんど気づくことができませんし、ユーリの父親とコマロフスキーの関係もセリフのところどころに出てくるだけでしっかり理解するところまでは行きませんでした。主人公の基本的人間関係を伝えきれなかったのはロバート・ボルトの脚本の不備が原因ではないでしょうか。
加えて本作を支えるユーリとラーラの恋愛関係はひと言で表現するなら「不倫」です。ラーラは行方不明になった夫を探しに看護師になり、結果的に夫はストレルニコフという革命家として生きているにも関わらず、ユーリと不倫関係に陥ります。またユーリの子どもを宿しているとは言ってもコマロフスキーとともに辺境に逃げ延びた後は、どうやらコマロフスキーとヨリを戻して夫婦として暮らしていたようです(ユーリの娘トーニャの手を離したコマロフスキーは本当の父親ではないと語られますので)。ラーラが結果的に男を乗り換えていた現実はジュリー・クリスティの存在感で帳消しになっていますが、よくよく考えてみると本心はどうだったのかと考えさせられます。
一方のユーリも幼いころから結婚することが決まっていた妻がありながらラーラを忘れられないという心境は、トーニャからすればずいぶん自分勝手に思えるでしょう。なんとなくトーニャもその不倫に気づいていて、でも夫を責めたりしないのはちょっと前時代的だなと思わされます。また序盤だけで姿を消していたコマロフスキーが突如終盤に姿を見せて、ラーラを救うために列車の座席まで用意するという親切心はどこから来ているんでしょうか。その後夫婦的に暮らしていたとすれば、ラーラの若い肢体を忘れられなかったという肉体的な欲望だけがあったのかなと勘繰ってしまいます。
セリフではラーラがストレルニコフの妻であることで常に監視されていることが語られますが、それを思わせるのはラーラのアパートの外で男が煙草を吸っているワンショットのみでした。ユーリが捕縛されるときも不倫関係は見破られていたので、もう少しラーラが監視下にあったという緊迫した状況を映像で見せてくれた方が映画の後半にサスペンス感が増したのではないかと感じます。
とは言え、デヴィッド・リーンお得意の歴史を描きながらもその流れに抗うようなひとりひとりの人生があったのだ的な叙事詩的大河恋愛ドラマの風格は十分に備わった名作であることに違いはありません。3時間17分の長尺に耐えられるかどうかが本作を鑑賞する際の一番のポイントですので、できれば映画館の大画面で見ることをおススメしたいと思います。(T020925)

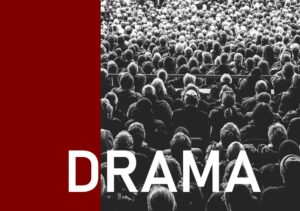
コメント