小林正樹の監督昇格後四作目は木下恵介の実妹楠田芳子が脚本を書いています
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、小林正樹監督の『この広い空のどこかに』です。小林正樹は昭和27年に中編『息子の青春』で松竹で監督に昇格しました。本作は小林正樹監督にとって四番目の作品にあたり、佐田啓二が営む酒屋に嫁いだ久我美子と酒屋の家族との日常が描かれています。脚本を書いた楠田芳子は木下恵介の実妹で戦時中にキャメラマンの楠田浩之と結婚して楠田姓となり、本作が脚本家楠田芳子のデビュー作となったのでした。
【ご覧になる前に】佐田啓二の妹役は高峰秀子、弟役は石浜朗が演じています
川崎駅に近い商店街にある森田屋酒店では近所の主婦が気が利かない嫁のことを愚痴りながら味噌を買っています。主人良一がスクーターで集金に出かけるので妻のひろ子が朝食を出しますが、みそ汁は母が作ったものでした。良一の妹やす子は空襲で足を悪くし婚期を逃して実家にいて、呑気なひろ子のことをしつけるよう母に言います。二階では良一の弟のぼるがまだ布団で寝ていて、ひろ子がカーテンを開けると飛び起きて布団をしまって出かけていきます。のぼるには三井という苦学生の友人がいて、二人は寺の階段でパンをかじるのでしたが…。
小林正樹は田中絹代とはまた従弟の関係で、松竹を受けるときに田中絹代を頼ったものの、コネで入社しても映画界では通用しないと指摘され、親戚であることを隠して見事助監督として採用されました。入社後まもなく兵役にとられますが、戦後復員すると木下組につくことになります。木下組では監督がスタジオに現れたときに、すぐに「よーい、スタート」の声がかけられるよう準備することが助監督に求められていたそうですが、小林正樹はそれを完璧にこなし、一日の撮影スケジュールをまとめた一枚の大きな紙を木下恵介にサッと渡すような優秀な助監督でした。
小林正樹の監督デビューは昭和27年の『息子の青春』という5巻もので、二作目の『まごころ』は木下恵介が脚本を書いています。まず中編からスタートさせ、本格的な長編では師匠から脚本を提供されたわけで、木下恵介がしっかりと小林正樹の監督としてのキャリアを後押ししていたことがわかります。そして四作目となる本作は、木下恵介の実妹楠田芳子のはじめての脚本作品でもあり、同じく木下組の優秀助監督の一人である松山善三(クレジットでは松山善太)が「潤色」という形で楠田芳子をアシストしています。もちろん音楽は木下忠司ですから、木下恵介が小林正樹のために、楠田芳子、松山善三、木下忠司を勢揃いさせて、その盤石の体制の下で楠田芳子を脚本家としてデビューさせたのでした。
ただし、キャメラマンだけは楠田芳子の夫であり、木下恵介の義弟になった楠田浩之ではありません。清水宏監督のもとで撮影助手から撮影技師に登用された森田俊保がキャメラを回していまして、清水宏が松竹を離れたあとは主に原研吉監督についていた人でした。小林正樹監督作品では『まごころ』に次いで本作は二回目のコンビとなり、『美わしき歳月』『泉』と連続して小林作品の撮影を担当することになります。
主演の佐田啓二は同じ年の春に『君の名は』三部作を撮り終えたところで、松竹を代表する大スターになっていた頃で、年間10本くらいの作品に出演していました。久我美子は早い頃からフリーの立場でしたので、本作の前後には東京映画や大映、東映など映画会社の枠にとらわれずに活躍しています。さらに高峰秀子の出演歴をみると、本作の前に木下恵介の『二十四の瞳』に主演して、本作の次には成瀬巳喜男の『浮雲』に出ているんですよね。日本映画史の中でもトップランクに位置する名作の合間の出演作ということに本作の価値があるような気がしてきます。
また弟を演じる石浜朗は、高校在学中に応募した『少年期』という作品で映画に初出演し、その演技が好評で松竹専属になったんだそうです。本作はその三年後の出演作で石浜朗は十九歳ですから、ちょうど本作の学生役にぴったりの歳でした。本作以降、小林正樹監督作品では『人間の條件』に出ていますし、なんといっても欠かせないのが『切腹』の婿役でしょう。そのほか、日守新一や小林トシ子など松竹おなじみの俳優が出ていますし、大映から浦辺粂子、東宝から中北千枝子を借りたりして、なかなか豪華な俳優陣で構成されています。
【ご覧になった後で】悪人が出てこないヒューマンタッチなホームドラマです
いかがでしたか?佐田啓二が切り盛りする酒屋の家族をはじめ、近所の人やひろ子の実家の信州から訪ねてきた幼馴染ややす子の学校時代の友だちはみんな良い人たちばかりで、悪人がひとりも出てこないホームドラマでしたね。前半では高峰秀子演じるやす子が足が悪いことに引け目を感じる陰湿な役回りでしたが、大木実演じる俊どんが現れる後半には急展開してしおらしくなっていき、静岡の山間部で逞しく生きるという筋書きになります。昭和29年はまだ戦争を引きずっている頃ですので、高峰秀子の足が悪いのも空襲での怪我がもとになっていましたし、肉体労働の飯場で働く中北千枝子は夫が戦争から帰還せず女手一つで子どもを育てているという設定でした。そんな中でも森田屋酒店の家族が朗らかに生きていくという希望を感じさせる物語が、当時の庶民の慎ましい幸せのような感じを醸し出していました。
特に佐田啓二が一家を支える主人役を優しく頼もしく演じていたところに好感がもてました。超二枚目で前髪が垂れたりしているのに非常に誠実で実直な人物になり切っていて、ひょっとしたら『君の名は』の春樹役のイメージから脱却しようとしていたのかもしれません。久我美子は同じ年に出た『女の園』での勝気な女生徒や二年後の木下恵介監督作品『夕やけ雲』での自分勝手な長女のような役も演じられる巧い女優さんですけど、やっぱり本作のような朗らかでちょっとお茶目な若奥さん役が一番お似合いのような気がします。
石浜朗が稚拙ながら清々しい演技見せる一方で、田舎に帰る友人を演じた田浦正巳の憂い顔が印象的で、ちょっとエキゾチックな雰囲気のある美青年なのに影のある役をうまく表現していました。木下恵介の『日本の悲劇』でデビューした翌年の出演作にあたっており、このあとに小津安二郎が『早春』や『東京暮色』に出演させたのもなんとなく肯けるような感じがします。
清涼感のあるヒューマンタッチなホームドラマにケチをつけるのは気が引けるのですが、とはいっても細部をみると甘いなあと感じさせる点がいくつもあって、全体的にはプラスとマイナスでゼロくらいの出来栄えになっていたのではないでしょうか。というのも佐田啓二は森田屋酒店のことを田浦正巳の苦学生と同じように貧しいと主張していますが、商店街に店を構えた家は二階建てですし、浦辺粂子と高峰秀子は「奥」と称する離れのような部屋に居住しています。図面で起こせばかなりの広さのある立派な家にも思えます。
「奥」には高峰秀子の琴が立てかけてありますし、ちょっとした庭もあり、土間の台所もそれなりです。高峰秀子は琴だけでなくお花のお稽古にも通っていたというセリフが出てきて、浦辺粂子は佐田啓二のことを税金を支払うのでも大変なんだと労います。税金を払うのが大変ならかなりの収入がある酒屋ということになりますよね。石浜朗は大学に通わせてもらっているようですし、田浦正巳にはコンビーフ缶をもっていってやり、久我美子の様子を見にきた内田良平は当時高級だったであろうウイスキーをもらっています。
そして極めつけは中北千枝子にポーンと5千円をあげてしまうところ。後で信州のお父さんのために貯めたということがわかるのですが、佐田啓二はちょっと迷うものの、それなりの大金も用意できるゆとりある生活なのは間違いありません。となると、貧しい人たちが互いに助け合うというよりも、森田屋の人たちが善意ではあるけれども困った人たちに施しを与えるというような、ちょっと偽善っぽさが感じられてしまうのでした。
これは楠田芳子の脚本の甘さなんだと思うわけでありまして、例えば中北千枝子は雨の中で公衆電話をかけている姿が映った以降一度も姿を現しません。酒屋にやってきて、少ないけれどもまず10円お返ししますみたいなこと場面が出てくるのかと思って見ていたのですが、結局5千円は貰いっ放しです。田浦正巳は田舎に帰るというので酒屋に挨拶に来たとき、いろいろおいしいものを分けていただいてありがとうございますみたいに言うのかと思ったら、自分のことだけ告げて去ってしまいます。なんだか貧しい人たちは森田屋酒店に感謝もしないように見えてしまい、それは酒店の家族が施しと思っているからなのではないかという気がしてくるのです。
結婚したばかりの女性の家をわざわざ信州から出てきて訪ねていき、無言で見ている内田良平は、現在的にはストーカーのようにしか見えません。まあ真面目で朴訥な青年だとしても、出された酒をそのままにして夜の街を久我美子と歩いて行ってしまうとしたら、佐田啓二の立場なら怒るか不機嫌になるかするのが普通でしょう。でもそんな態度は見せずに佐田啓二は笑顔で内田良平にウイスキーを手渡すのです。あまりに美談過ぎて普通の人の感情がないのではないかと疑ってしまいますし、なんだか嘘っぽく感じられました。
佐田啓二と久我美子が物干し台から「お金のない人に届け」とか「病気の人にも」とか言いながら幻のボールを投げる恰好をする場面。佐田啓二と久我美子の爽やかな表情もあって本作屈指の名場面ですが、やや意地悪な見方をすると世の中の人がすべて平等に幸せになる権利があるんだ的なイデオローグを教宣しているようにも見えてきますし、この夫婦は幸せを分配するような高みにいる気になっているのかと勘繰りたくなってきます。なんだかリアリティのない空疎な理想論だけを振り回している感じでした。
もちろん昭和29年という世相の中で出てきた作品ですので、このような捉え方は偏屈過ぎるんでしょう。豊かではない暮らしの中で、週に一度映画館で本作のような映画を見て、次の一週間をがんばろうという希望がうまれたのかもしれません。そういう映画だったとしても、現在的には斜めから見るとちょっと違った様相が出てきてしまいます。そう考えると普遍的に楽しめる映画というのが名作といわれる前提となるんだなとあらためて感じた次第でした。(U020525)

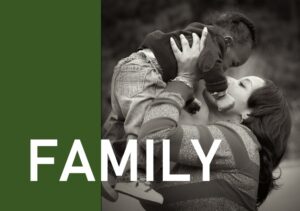
コメント