家を奪われた老夫婦が子供たちに別々に引き取られる普遍的ホームドラマです
こんにちは。大船シネマ館主よのきちです。今日の映画は、レオ・マッケリー監督の『明日は来らず』です。老いた両親の世話を成人して家庭もある子供たちが引き受けるといういつの時代にもある普遍的な社会問題をのんびりとした雰囲気で描いていて、多くの映画作家から愛されている作品です。レオ・マッケリーは第10回アカデミー賞監督賞を獲得していますが、対象作品は本作と同じ年に撮った『新婚道中記』で、本作に愛着を抱いていたマッケリーは「間違った作品で受賞してしまった」と嘆いたと語られています。
【ご覧になる前に】小津安二郎が『東京物語』の参考にしたと言われています
ジョージが一軒家に入ると、そこには両親を囲んで四人の兄弟が集まっています。ネリー、コーラの妹二人を弟のロバートがからかう中で、父親のバークレイは退職して収入がなくなり借金が払えなくなったので家を手放さなければならなくなったと告げます。両親の面倒を誰がみるのか、四人の兄弟は考え込みますが、結局父親はコーラが、母親のルーシーは長兄のジョージが引き取ることになりました。ジョージには妻アニタと娘ローダがいて、アニタはルーシーが話の邪魔をするのでローダが自宅に友達を連れて来なくなったと嘆くのですが…。
小津安二郎監督の『東京物語』は本作を参考にして製作されたと言われていて、実際に小津安二郎とともに脚本を書いた野田高梧は「戦前に公開された『明日は来らず』を僕だけが見ていて、それもうろ覚えだったんだが、それがシナリオのヒントになった」というようなコメントを残しています。確かに家を失くした老夫婦を子供たち兄弟の誰が世話をするのかという設定は、本作そのものだと言えるでしょう。しかし小津安二郎は池田忠雄と共同で書いた『戸田家の兄妹』は、急死した父親のあとに残された母親と末妹が兄弟の間をたらい回しにされる話ですので、一概に『明日は来らず』が『東京物語』の元ネタであると言うことはできないでしょう。まあ小津は多くのアメリカ映画からインスピレーションを得ていますので、本作もそのうちの一本だったという程度だったんではないでしょうか。
とは言え本作は多くの作家たちから高く評価されていて、劇作家のバーナード・ショーはわざわざレオ・マッケリーに賞賛の手紙を書いたそうですし、オーソン・ウェルズは「石さえも泣かせる映画だ」と評しました。ほかにもジョン・フォード、フランク・キャプラ、ジャン・ルノワールといった名監督たちが本作に大いなる賞賛を寄せていたようです。
レオ・マッケリーはサイレント時代のドタバタ喜劇を数多く監督した人で、特にローレル&ハーディのスラップスティックコメディの名手でした。1935年の『人生は四十二から』以降はヒューマンタッチのドラマに路線転換して、この『明日は来らず』もマッケリーにとって自信作だったんだとか。ところが興行的に惨敗し、スクリューボール・コメディの『新婚道中記』でオスカーを獲得したときには本作にこそ賞が与えられるべきだったと発言したそうです。1944年にはビング・クロスビー主演の『我が道を往く』で二度目の監督賞を受賞し、名声を確固たるものにしています。
ヴィナ・デルマーという人の原作をジョセフィン・ローレンスとヘレン・リアリーの二人が脚色したそうで、原作もシナリオも女性の手によって書かれています。野田高梧は本作のことを「保険会社の養老保険の宣伝映画」だと記憶していたようで、現在のような年金制度が普及していない1930年代前半のアメリカ市民の暮らしぶりを描くには女性のほうが適材だったんでしょうか。アメリカで社会保障制度が導入されたのは1935年のことで、フランクリン・F・ルーズベルト大統領が署名した法令は改正をされながらも現在でも有効になっています。
主人公のクーパー夫妻を演じるのは、ヴィクター・ムーアとビューラ・ボンディ。撮影当時ムーアは六十一歳と劇中の設定とほぼ同じ年齢でしたが、ボンディはまだ四十八歳で、娘コーラを演じた女優より一歳年下だったそうです。それでもしっかり老母役を演じているのはメイクアップ技術のなせる技でしょうか。また長兄ジョージ役をやるトーマス・ミッチェルは、二年後の1939年には『駅馬車』で飲んだくれの医師役を演じてアカデミー賞助演男優賞を受賞していますし、『真昼の決闘』でゲーリー・クーパーに町を出るように勧める町長役を演じたことでも有名です。
【ご覧になった後で】リアルな現実から心温まるロマンスへの転換が見事です
いかがでしたか?社会保障制度が確立していない時代で年金もなく老後のための貯蓄をしていなければ頼りになるのは子供だけという設定が身につまされますし、自営業でもなく手に職も持たない老人に働き口がないというシリアスな設定もリアルな現実を感じさせます。冒頭では慈母のように見えたルーシーが次第に口うるさい姑みたいな存在に見えてくるのは、観客がジョージの妻アニタに感情移入してしまうせいかもしれず、アニタが「あの子は私の娘であって、あなたのものではありません」と口にしてしまうのももっともだと感じてしまいます。
父親のバークレイのほうは、普段はソファに寝かされているのに医者が往診に来ると体裁を整えるために寝室のベッドに移されるところが、シニカルな笑いを感じさせました。妻と離ればなれになったバークレイの話を聞いた新聞売りのマックスが、台所にいる女房の名前を愛おしげに呼ぶあたりも含めて、父親側の描写にはユーモアがあって、女性のライターたちが書いた脚本なので、女性の立場のほうがより厳しめに描かれたのかもしれません。
老親の介護は現在でも切迫した社会問題なので、なんとなく沈鬱な雰囲気で進むものの、久しぶりにバークレイとルーシーの二人が会って公園を散歩するあたりから、本作は急にウェルメイドなロマンスものに変化し始めます。ここからは子供たちの存在はほとんど無視されて、老いた夫婦が互いに愛し合い、尊敬し合い、互いになくてはならない大切な人であることが痛いほどに伝わってきます。思い出を語り合い、水曜日か木曜日かで口論する姿からは、長年の信頼が感じられ、ヴィクター・ムーアとビューラ・ボンディの芝居の巧さが最高潮に達します。本当に見ていても心温まるようなぬくもりが伝わってきました。
バークレイがルーシーのことを「ブレッケンリッジ嬢」と結婚前の名前で呼ぶのもいいですよね。ここらへんは本当に脚本の巧さですが、列車に乗った夫を見送ったあとのルーシーの表情は、これでもう夫と会うこともなく老人ホームで寂しく死んでいくんだという悲しい未来を予測させるには十分過ぎるほどでした。本作は主人公二人の名演技を堪能させるために、ほとんどTVドラマのような平板な演出しかされていません。それが本作を現在でも価値ある作品にしているような気がしますね。
また本作は悪人が出てこないところも大いに評価したいところです。自動車を売りつけようと夫妻を車に乗せる中年男は、ホテルまで連れて行く車中での夫妻の会話にすっかり和んでしまい、車を買わせようとしたことなど忘れます。ただ単に運転手代わりに使われた形なのに良いことをしたというように夫妻を見送ります。ホテルのレストランでは支配人が二人の会話の相手になり、ダンスホールの楽団の指揮者は、二人がルンバのリズムに合わせられないと気づくと、またゆっくりとしたワルツに曲を戻します。新聞売りのマックスだけでなく、親切な人たちに囲まれて最後のデートを楽しむ老夫婦が祝福されるような作りになっているのも、本作の見どころでした。
原題は「Make Way for Tomorrow」で「明日への道を拓け」みたいな意味ですが、『明日は来らず』は未来に対して否定的な邦題です。しかし映画を最後まで見ると『明日は来らず』のほうが本作のテーマを表現していることがわかります。パラマウント社の社長アドルフ・ズーカーは暗い終わり方ではなくハッピーエンドにするようレオ・マッケリーに圧力をかけたそうですが、マッケリーはそれを無視して、結果的にパラマウントはマッケリーとの契約を更新しなかったんだとか。それでもルーシーが暗い表情で立ち去るエンディングを貫いたことが本作の成功の要因だったと言えるでしょう。(A050525)

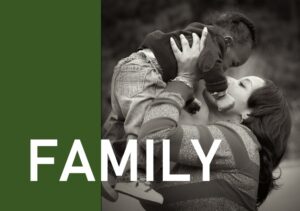
コメント